|
「南極は料理人を孤独にするか」 について
最近見た映画の中では、『南極料理人』がとてもよかった。普通に笑える程度に。
……まあ、そんなに映画見るほうじゃないんだけど。
というか、これ2009年の映画だから最近ともいえないんだな、とあとで気づいた。それはともかく、映画『南極料理人』の話である。以下、ネタバレ含むので注意。
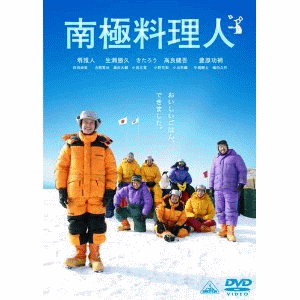 『南極料理人』(wiki) 『南極料理人』(wiki)
監督、沖田修一。主演、堺雅人。2009年公開。
情熱大陸で堺雅人の回を見たときに、この映画のために体重を何キロだか増やした、というのを覚えていて、頭の隅にひっかかっていた。たまたまBSでやっていたので、見てみた。面白かった。というのが経緯。
簡単に紹介すると、舞台は南極の標高3000メートル以上にある基地「ドームふじ」。主人公の西村(堺雅人)はそこに派遣された料理人で、基地にはほかに七人の人間がいる。世界の果てみたいな場所(というか果てだけど)で、八人の人間がドームという閉鎖環境で暮らしている、というのが全体の設定。というかbased
on 実話、というやつ。
この映画を見てから原作の『面白南極料理人』も読んでみた。何せブック・オフに百円で売ってたものだから。どうでもいいけど、基本的に値札がきれいにはがせないのでブック・オフの古本はあんまり好きじゃない。本を愛しているとかいうCMを思い出すと、「嘘つきやがれ!」と失笑、というか激昂してしまう。しかしそんなことも言っていられず、どうせ中身が変わるわけでもないし、ここは泣く泣く……いや、こんな話はどうでもいい。
ともかく、原作もけっこう面白かった。つまり、普通に笑える程度に。雰囲気的には大体映画と同じで……というか実際は逆だけど、原作・映画ともによい出来だった。
手前味噌だけど、これは映画を見てから原作を読んだほうがいいかもしれない、と思う。映画を見て、「ああ面白いな、これの原作ってどうなんだろう」という流れが理想かと。原作読んでからだと、「ここ変えたんだな」「ここは原作と違うな」とか、そんなことが気になって素直に見れなくなるかもしれない。まあ、個人によるところではあるけど。
にしても、原作読むと何だか宴会ばっかりやってるような……「何で松坂牛なんて食ってんだよ」と。
面白いからいいけど納得できないようなところもある。それくらい許せるほど南極滞在は過酷だ、ということなのかもしれない。……映画も原作も全然、そんな感じじゃなかったけど。
映画も原作も、基本的には南極基地での日常生活、というのが主点になる。生活自体は寸劇的に描写される。実際にはどうかは知らないけど、何だか遊んでいるようにしか見えない。
しかしドームふじは富士山より高所にある、−50℃とか−70℃とかの世界である。酸素は薄いし、ウイルスも生存できない、と書かれている。……まあ、もちろん大変なんだろう。どうしても三谷幸喜的な世界にしか見えないが。
そろそろ主題にかかる。全体的な内容なんかは、実際に見てもらえばそれでいいかと思う。
この映画を見て僕がどうしても気になったのは、「料理」の扱われかたである。
最初のほうに朝食のシーンがあるのだが、これがなんというか、その、とても雑な食いかたなのだ。
「ぐちゃぐちゃ」という擬音が聞こえてきそうなくらい、みんな飯を「かきこんでいる」。どう見ても、「味わっている」ようには見えない。
で、そんな食事風景をずっとカメラが追いながら、最後に料理人である堺雅人の姿をとらえる。堺雅人はなんともいえないような顔をしている。映画を見ている人間がその心の声を代弁するなら、「みんなもっと、きちんと食えよ!」である。
でも最後まで不思議だったというか、よくわからなかったのは、この堺雅人(西村)がそれをどう思っているのかが不明だった点である。
堺雅人は最後まで、「もうちょっとうまそうに食えよ」とか「せめてもう少し味わって食えよ」というようなことは言わない。ちょっとだけひきつったような顔をしているだけである。それも、本当にひきつってるのかどうかはわからない。表情がほとんど読みとれない。
この点が、僕は今でもひっかかっている。
もうちょっと細かい点を見ていく。
まず、この料理人の堺雅人は、好きで南極に来たわけではない。直前になって怪我をした同僚の代役として基地にやってくる。本人は家族と離れるのが辛くてたまらなかった(はず。でも家族がひきとめなかったので、結局この任務につく)。
つまり映画の最初の頃は、堺雅人は「あくまで義務」として料理をつくっている。
この辺は原作とは違っていて、原作者の西村さんは、のりのりで料理をつくっているし、はっきりいって南極生活を「楽しもう」としている。そもそも、料理は当番制だったみたいで、映画のように料理人が一人でつくっているわけでもない。
原作との違いはともかく、映画での堺雅人はどちらかというと「不遇な料理人」という立場にある。注意して見ていたのだけど、映画の中では誰も「うまい」と言わないのだ。本当に、言わない。最後まで言わない。言ってもらえない。
僕はこの映画を見ていて、テーマは「孤独」にあるのだと思った。
まあ個人的にそこが一番気になった、というだけの話。
南極という超僻地で、人口がたった八人だけの世界。人間のいる場所ははるか遠く。
そんな中で、料理人はさらに孤独な状態に立たされる。つまり、料理人にとってもっとも重要な「料理/『うまい』の言葉」から切り離されているのである。
つまるところ、彼は「料理人」ですらない。
そういう点で一番印象深かったシーンは、生瀬勝久の演じる隊員の一人から、憫笑めいた表情でこんなことを言われるシーンである。
「――西村君さあ、別に飯食いに南極に来たわけじゃないからさ」
この一言が衝撃的だったのは、それが完全な「料理人の否定」であったのと、「料理人としてのエゴ」を露出させる効果を持っていたこと。つまり、「もっときちんと食え」という心の声は、とりもなおさず「ありがたく食え」という感情と表裏一体だった、ということ。
ある意味ではこの「正当性をもったエゴ」が料理人を「孤独」にしている、という事実。
このシーンのあと、堺雅人が倉庫のダンボールを軽く横蹴りする場面があるが、それが「内心の苛立ち」を表しているのかどうか、僕にはよくわからなかった。たぶんそうだとは思うのだけど、どうもすっきりしていない。
話が進んでいくと、ラーメンのことが問題になる。
隊員の中に即席ラーメンを大量に消費している人間(隊長ともう一人)がいて、在庫が底をつきてしまう。麺を作るにはかん水が必要で、基地にはそれがない。
ところが、きたろう演じるこの隊長が、突然寝ている堺雅人の部屋をノックして、今にも泣きだしそうな顔でこう言う、「僕の体はね、ラーメンでできてるんだよ」
知らんがな、そんなこと、と見ている僕は思ったが、堺雅人がどう思ったのかは知らない。カメラが徐々にきたろうの顔をアップにしていくシーンは、どっちかというと「こっち見んな」状態だったけど、事態としては深刻である。隊長はラーメンがなくなって以来、元気をなくしていく。
つまりこれは、ラーメン=人間の世界、を象徴しているのだ。隊長の鬱状態は、人間としての孤独、のメタファーでもある。
……たぶん。
最終的に、ラーメンは作られる。ベーキングパウダーをかん水の代用として使用する。
ここが映画としての一応のクライマックスで、信じられないようなオーロラもそっちのけで、みんなでラーメンをすする。
みんな幸せそうである。堺雅人も満足そうである。
でもここでも、誰一人として「うまい」とは言わない。
実はこの映画で唯一「うまい」のセリフが聞こえるのは、ラストの場面である。本当に、一番最後のシーンなのだ。
それは、堺雅人が日本に帰ってきて、家族で動物園に行ったときのこと。昼に園内のカフェテリアでハンバーガーをほおばるところで、堺雅人が一言、「うまっ」
このシーン、実のとこ最初はなんと言ったかわからなくて、巻き戻してみた(録画したものを見ていた。どうでもいいけど、ディスクなのに巻き戻すって言いかたは変な気もする。……どうでもいいけど)。何と言っているかわかったのは、二回目に見たときのこと。
これは、さっき言った「料理人/うまい」の関係性を適用した、「孤独からの回復」としての表現なのだ。
つまり、この映画では「うまい」から切り離された料理人の孤独、が全体的なメタファーとして機能している。視聴者は南極隊員の孤独を、主人公である料理人の、料理人としての孤独から読みとる。この映画の「孤独」は「南極世界/人間世界=料理人/うまい」の構図になっているのだ。
「うまい」は、とりもなおさず「人間世界」の記号として機能する。この二つは等記号で結ばれる。
だから、最後の「うまっ」は「帰ってきた」ことの表現でもある。それも念の入ったことに、動物園でハンバーガーを食ってのシーンなのである。これほど人間世界を象徴する対比もない。
もう一度言うが、これは人間の「孤独」をテーマにした映画である。それも、料理人というメタファーを使った孤独の……
――と、いうようなことを思ったのだが、何だか違うような気もしている。
映画についてのインタヴュー記事を見ると、そういう主張は片鱗も感じられない。主演の堺雅人いわく、「この映画のメッセージはとてもシンプルで、『皆で食べるご飯は美味しいね。大切なことだね』」ということなのだという(こちら)。
まあ確かにそうなんだけど。
監督にしても、「彼らの食べ方があまり美しくない気がしたのですが、これは演出なんですか?」の質問に対して、何の屈託もなく「豪快に食べるというのは前提でした」と答えている(こちら)。
どうも、別にうまくなさそうにしているわけではないらしい。
というより、あれは「うまそうに食べている」表現だったようだ。
僕がこの映画に感じた違和感。何もないところで転んで、地面をさすってみたけどやっぱり何もない感じ――
それはあるいは、まったくの見当違いなのかもしれない。ただこの映画を、自分を映す鏡として利用しただけのような。
一応は、最後の最後で出てきた、「うまっ」が一体なんだったのかを考えた結果ではあるのだけど。
まあ、いろんな見方があるのだから、それは別にかまわないのだろう。
けどやっぱり、あれは「うまそうに食べている」ようには見えなかったけどなあ…… | 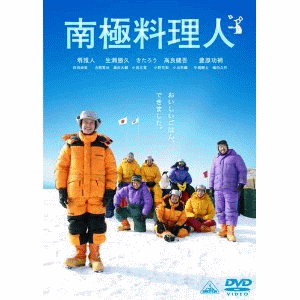 『南極料理人』(
『南極料理人』(