|
「玩具と自由度と子供時代」 について
これは昔々、まだゲームが子供の玩具だった頃のお話……
※
さて、表題からはわかりにくいと思いますが、ここで問題にしたいのは、ゲームにおける「自由度」についてです。
「自由度」
と、いきなりいってもわかったようなわからないような感じですが、先に言っておくと、ここでの「自由度」は概ねDQ3(DQ=ドラゴンクエスト)的なものを念頭にしています。
ストーリーに縛りがない、マップ移動にしばりがない、キャラクターに縛りがない。
自由度といっても連想はいろいろです。例えばロマンシング・サガ的な、大通りのないゲームや、マルチエンディング的なものをそうだという人もいるかもしれません。
ただ、僕が考える「自由度」はそうしたシステム的なものより、雰囲気としてのそれに近いかと思います。空気感というか、世界観としての自由度、とでもいえばいいのか……
だからここでいう「自由度」は、正確な意味での自由度というわけではありません(正確な意味での自由度がいったい何なのかもよくわかりませんが)。
で、僕の感じている「自由度」にもっともぴったりくる言葉は何だろうと考えていたら、こんな言葉が浮かんできました。
「冒険感」
言葉そのままなんですが、なんというか、冒険している感じ、です。つまり、ゲームの主人公がダイレクトにプレイヤーになって、「モンスターを倒したり」「洞窟を探検したり」する感じ。
仮想的というより、現実的な感覚に近い。それは、子供が押入れの中に入って別の世界を幻想するような、そんな感じです。現実を仮想化するのと同じ場所に、仮想を現実化する。ゲームの中で剣を装備したり、船に乗ったりしているとき、現実のプレイヤーもそれと同じ経験をしている。
僕が自由度の高いゲームに感じる(あるいは、それがある場合に「このゲームは自由度が高い」と感じる)のは、そういうものである気がします。
「自由度」=「冒険感」
これを主軸にして、少しゲームにおける自由度について考えてみたいと思います。
※
さて、とりあえず具体例を見ていくのがいいと思うので、冒頭にあげたように「DQ3(wiki)」をとりあげてみます。
 なぜ、DQ1・2や4・5でなく3なのかというと――僕にもよくわかりません。たんに一番印象に残っている、というだけの話のような気もします。いわゆる「思い出補正」というやつですが、ここではそれ自体はいったいん棚上げにしておくことにします。 なぜ、DQ1・2や4・5でなく3なのかというと――僕にもよくわかりません。たんに一番印象に残っている、というだけの話のような気もします。いわゆる「思い出補正」というやつですが、ここではそれ自体はいったいん棚上げにしておくことにします。
僕がDQ3に感じる「冒険感(=自由度)」は先に言ったとおり「現実感に近いもの」、です。
実際にフィールドを歩いたり、宝箱を開けたり、宿に泊まって回復したりする感じ。レベルアップすると自分も強くなる感じ、全滅したときの挫折感、新しい町や城にたどりついたときの安心、初めて足を入れるマップでの緊張。
そうした一体感。一言でいってしまえば、自分も実際にそのゲームの中に入れればいいのに、という感じ。
臨場感といったものとは違う、もっと生に近い、あるいは、幻想性の強い状態、濃度の高い関係性。
DQ3における、「冒険感」はどこからやってくるのか?
ここで、DQ3における特徴を箇条書きにしていきたいと思います。
・しゃべらない主人公
・選択のない選択肢
・保護者
・進まない時間(くりかえす「一日」)
・大雑把な目的
・断片化、あるいは欠落した情報
前に「勇者はロールプレイさせられるから勇者になる」ということについて書いているので、「しゃべらない主人公」や「選択のない選択肢」については簡単に触れておくことにします。
DQ3では(3だけじゃないですが)、主人公にはあまり性格づけがされていません。というより、それは巧妙に避けられています。主人公は正義漢でも卑劣漢でも悪漢でも、天使でも悪魔でも、知識人でもブルーカラーでも、なまいきでもわがままでも従順でも欲張りでも、何者でもあるし、何者でもありません。
つまり、人形です。パーマンに出てくるコピーロボットよろしく、対象者によってその形象は自由に変化するのです(……ジョジョ第四部の間田のセリフではないにしろ、「パーマンのコピーロボット」はもうあんまり通じなくなってるんでしょうか)。
玉虫色の主人公は、ようするにアバターとしての機能を持ちます。着ぐるみ、姥皮、なんといってもいいですが。
そして「はい/いいえ」の無限ループはプレイヤーの強制承認を生みだします。つまり、現実ではどうあれ、ゲーム内ではその選択に納得せざるをえないのです。選択肢のない強制、ではなく、あくまで強制承認であることがみそです。一種のメタ設定としての機能、といっていいかもしれません。
では次に、「保護者」とは何なのか。
DQ3で一番特異なのは、母親の存在ではないでしょうか。
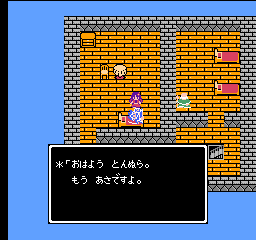 ゲームの冒頭で寝坊したプレイヤーをベッドから起こして、城まで案内し、いつまでも子供の帰りを待っている。 ゲームの冒頭で寝坊したプレイヤーをベッドから起こして、城まで案内し、いつまでも子供の帰りを待っている。
完璧なほど「母親」です。まるで子供を学校に送り出すみたいに。
この母親も、考えてみれば不思議な存在です。子供をたった一人で魔王退治になんて行かせて、夫は長いこと行方不明、あの狭い城下町に二階建ての一軒家を所持して、どうやって生計をたてているのかもわからない(戦没者年金?)、祖父(どっちのだろう?)と同居。
そして何より、圧倒的な存在感のなさ。
たぶん二つめの町(レーベ)に着く頃には、すっかりその存在そのものを忘れてしまっているような母親。ただで回復ができる他は何のイベントも変化もない母親(※と思っていたら、ちょっとセリフがあって、バラモスを倒したあとは泊めてくれなくなってますね)。
それをたんに容量の都合、と考えることは容易なんですが、どうもこの母親、今になって考えてみるとDQ3というゲームの世界観のほぼ中心にある、といっていい気がしているのです。
孫引きの孫引きになりますが、大塚英志の『ストーリーメーカー』に瀬田貞二の『幼い子の文学』からとして、『アンガスとあひる』という絵本が紹介されています。
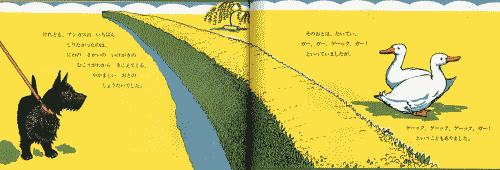
この絵本は、スコッチテリアのアンガスが、奇妙な音の聞こえる垣根のむこうに行って、あひるに会い、家に逃げ戻ってくる、というそれだけの話です。
これを読んだとき僕は、いわゆるジュブナイル小説というやつの根幹は、「保護者の有無」にあるのではないか、と思ったのです。保護者というか、別に人間じゃなくてもいいのですが、「主人公を守る存在」、あるいは「守られている存在としての主人公」。
それを「帰る場所」としてもいいのですが、僕としてはそれより「目線」の問題じゃないか、という気がするのです。
小さな砂場で一心不乱に遊ぶ子供を見つめる誰か。その子供でもあり、誰かでもある存在としての「目線」。
それがジュブナイルというか、最初に言った「冒険感」の重要な要素なのではないか、と。
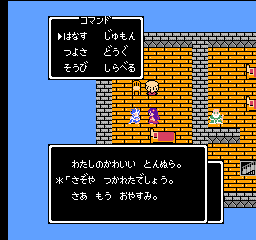 DQ3における「母親」は「小さな砂場で一心不乱に遊ぶ子供を見つめる誰か」のまさしくその「誰か」の目線です。 DQ3における「母親」は「小さな砂場で一心不乱に遊ぶ子供を見つめる誰か」のまさしくその「誰か」の目線です。
そして勇者は「小さな砂場で一心不乱に遊ぶ子供」。
つまり、勇者だけではこのゲームにおける(というか、このゲームで僕が感じる)「冒険感」は存在しないのではないか、という気がするのです。そのためには遊び手だけではなく、それを見守るもの、が必要なのではないか……
子供を送り出し、帰ってくるのをいつでも待っていてくれて、優しく眠りにつかせてくれるような。
そして子供にとって、時間というのは永遠に繰り返す「一日」でしかない。「大人になる」という大雑把な目的の中で、子供は自分ではそれと気づかずに母親に「見守られて」暮らしている。
だからこそ、「冒険感」とはあくまで子供のものなのかもしれません。
少なくともそれは、「帰る場所」や、「本来いるべき場所」から一歩踏み出した状態である、ということはできるわけです。
それがなければ、例え銀河の果てまで行ってきたとしても、「冒険」にはならないのです。
それから、うまく言えないんですが、DQ3には「世界観そのものが断片化されている感じ」、があります。
大抵の場合どうしても、「わかりやすい説明」を人は心がけてしまうので、例えば「すべてを知っている誰か」が「全部説明してしまう」ということがゲームでも小説でも、よくあることになります。
それ自体は、まあ当然といえば当然といえます。親切です。
でもこの親切が、「冒険感」を損なってしまうようです。
たぶんそれは、自分よりその誰か(つまるところ、作者)のほうが、この冒険について詳しいのだ、という劣等感を呼ぶからなのかもしれません。
ビックリマンが、実際には「物語の断片を集めること」だったことや、富野由悠季が登場人物の断片的な独り言で物語を構成することは、だから「冒険感」にとって有効な方法であるような気がします。
世界の秘密を解くのではなくて、世界の秘密を探すことのほうが、たぶん二重に面白くなるのではないでしょうか。
……というわけで、「冒険感」をDQ3にしか感じないのは、ある意味では当然のことなのかもしれません。
4は主人公が何者かでありすぎるし、5はいわずもがな。1・2も基本的に出自がはっきりしています。世界は定まっているように見えるし、ストーリーは見えないながらもレールの上を走っている。
念のために言っておくと、だからといって他のDQシリーズが面白くないとか、そういう話ではありません(……6以降は好きじゃないですが)。個人的には5が一番好きです。
でも、「冒険感」があるのは、やはり3だけです。それは「母親」の存在のせいのような気がします。つまり保護者の存在です。
あるいは音楽、グラフィック、その他いろいろな要素があるのかもしれませんが、一番大きいのはそういうことではないか、と。
ただ、リメイク作ではどうもそれを感じないので、必ずしもそれだけの問題ではない気もします。
※
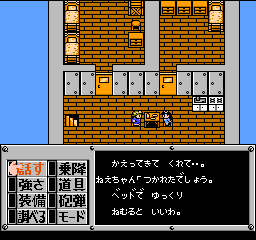 同じような「冒険感」のあるゲームとして、他にメタルマックス1・2(wiki)があります。 同じような「冒険感」のあるゲームとして、他にメタルマックス1・2(wiki)があります。
ややマイナーなところなので説明すると、要するに戦車の出てくるDQというところです。システム的なところや2Dキャラグラフィックなど、雰囲気的によく似ています(メタルマックス発売が1991年。DQ4・5の間くらいになります)。
で、このゲームでも面白いことに、「保護者」がいます。
メタルマックスは最初に、父親に家から放り出されるところからはじまるのですが、「ねえちゃん」がいて、これがDQ3の「母親」とほぼ同じ役割を果たします。つまり、子供を送り出し、帰ってくるのをいつでも待っていてくれて、優しく眠りにつかせてくれる、ということです。
2でもちょっとキャラクターは異なりますが、同じ役割の存在がいます。
あと、ちょっと主題とはずれるのですが、キングスフィールド2(wiki)にも同じような「冒険感」があります(1995年発売、フロム・ソフトウェア)。
プレイヤー視点のアクションゲームであることや、独特の緊張感がそれをもたらしているのかもしれません。とはいえ、これも1・3には何故か「冒険感」を感じないので、2に固有の特徴があるのかとも思います。
KF2が、剣を持って帰るという「おつかい」であることや、背景化された(というより借景、といったほうがいいのかもしれない)世界観が「冒険感」につながっている気がします。
似たようなゲームとして、マザー2やポケモンがありますが、どうしてだかそっちにはあまり「冒険感」を感じません。どちらにも「母親」が、同じような立ち位置で登場するのですが……
結局のところ個人差の問題なのかもしれません。好みとか、生育環境とか、そういう。
――とはいえ、もしもそこに重要な違いがあるとすれば、それは僕がそれらのゲームを「子供時代」にはやっていないこと、かもしれません。
※
最近のゲームでは「冒険感」を感じることは、ほぼなくなりました。
それは例えば、「親切なストーリー」や、「明瞭なグラフィック」「きちんと演出されたシステム」といったものに問題があるのかもしれません(……別に問題じゃないとも言えますが)。
高度化したゲームは、初期にあったような「玩具」ではなくなっているような気がします。
ゲームがファミコンであった頃は、それは双六や鬼ごっこといったものの延長でもあったと思うのです。スイッチを入れるとテレビにカラフルな画面の映る不思議な箱――初期のゲームハードを、そんなふうに言ってもいいかと思います。
だからこそ、それは「遊び」だった。道具は用意したから好きに遊んでくださいね、というような子供の自由が(意図的とはいえないにしろ)守られていた。
この辺のことは、今「子供」であるプレイヤーに訊かなければなんともいえないので難しいところですが、少なくともPS3のようなものを剣玉やメンコと同列に扱うのは、なかなか困難かと思います。
まあゲームが大人化する一方で子供向けのゲームも存在しているので、ゲームの「冒険感」がなくなった、とはいえないとは思います。携帯ゲーム機はいまだに「玩具」としての特性を保持している気もするので。
実のところ、僕は今でもDQ3をやると、当時の感情というか、「冒険感」をきっちり思い出すことができます。
そのこと自体は、とても不思議なことに思えます。
たぶんもう、それと同じ「冒険感」を新しく感じることはないだろうに、その時の「冒険感」自体は今でもきちんと保持されているのです。リスが地面に埋め忘れたどんぐりが、そのまま発芽もせずに残り続けているみたいに。
結局のところ、「子供時代」は永遠に残り続けるのでしょうか。
だとすると、「冒険感」のために何より必要なのは、「子供時代」なのかもしれません。いわゆる、「思い出補正」というものの正体は、この辺にあるような気がします。
とはいえ、こればっかりは自力で作れそうもないので、いったいどうしたものかと考えているんですが…… |  なぜ、DQ1・2や4・5でなく3なのかというと――僕にもよくわかりません。たんに一番印象に残っている、というだけの話のような気もします。いわゆる「思い出補正」というやつですが、ここではそれ自体はいったいん棚上げにしておくことにします。
なぜ、DQ1・2や4・5でなく3なのかというと――僕にもよくわかりません。たんに一番印象に残っている、というだけの話のような気もします。いわゆる「思い出補正」というやつですが、ここではそれ自体はいったいん棚上げにしておくことにします。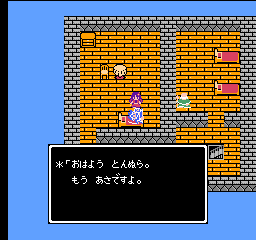 ゲームの冒頭で寝坊したプレイヤーをベッドから起こして、城まで案内し、いつまでも子供の帰りを待っている。
ゲームの冒頭で寝坊したプレイヤーをベッドから起こして、城まで案内し、いつまでも子供の帰りを待っている。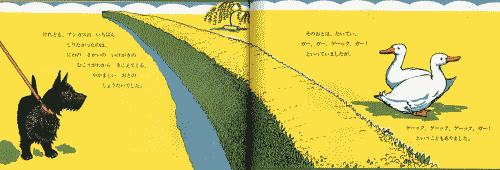
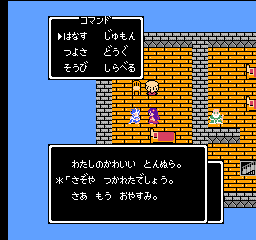 DQ3における「母親」は「小さな砂場で一心不乱に遊ぶ子供を見つめる誰か」のまさしくその「誰か」の目線です。
DQ3における「母親」は「小さな砂場で一心不乱に遊ぶ子供を見つめる誰か」のまさしくその「誰か」の目線です。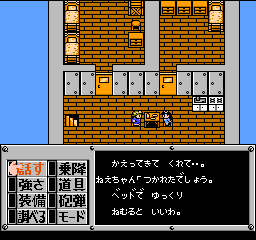 同じような「冒険感」のあるゲームとして、他にメタルマックス1・2(
同じような「冒険感」のあるゲームとして、他にメタルマックス1・2(