|
「2023年の読書記録」 について

2023年に読んだ本は、40冊。合計金額は11761円。
やんぬるかな。
と、呑気に言ってられるほどでもない。わりと、真剣に危機感を抱いている。
読むことの意味、生きていることの意味そのものに対して、煮えきらないところがあって、心をうまく働かせずにいる。いくらネジを巻いても、歯車そのものが壊れてしまった時計みたいに。
そして、そんなことを思っている時点で、やっぱり意味なんてないんじゃないか、と――
負のスパイラルというやつでもある。トラがお互いを追いかけはじめたら、最後にはバターになってしまうしかない。
もう言い訳すら、うまくできなくなってしまっている。
ともかくも、印象に残った本について書いていこう。
少しでも、そうしたいと思えているうちは。
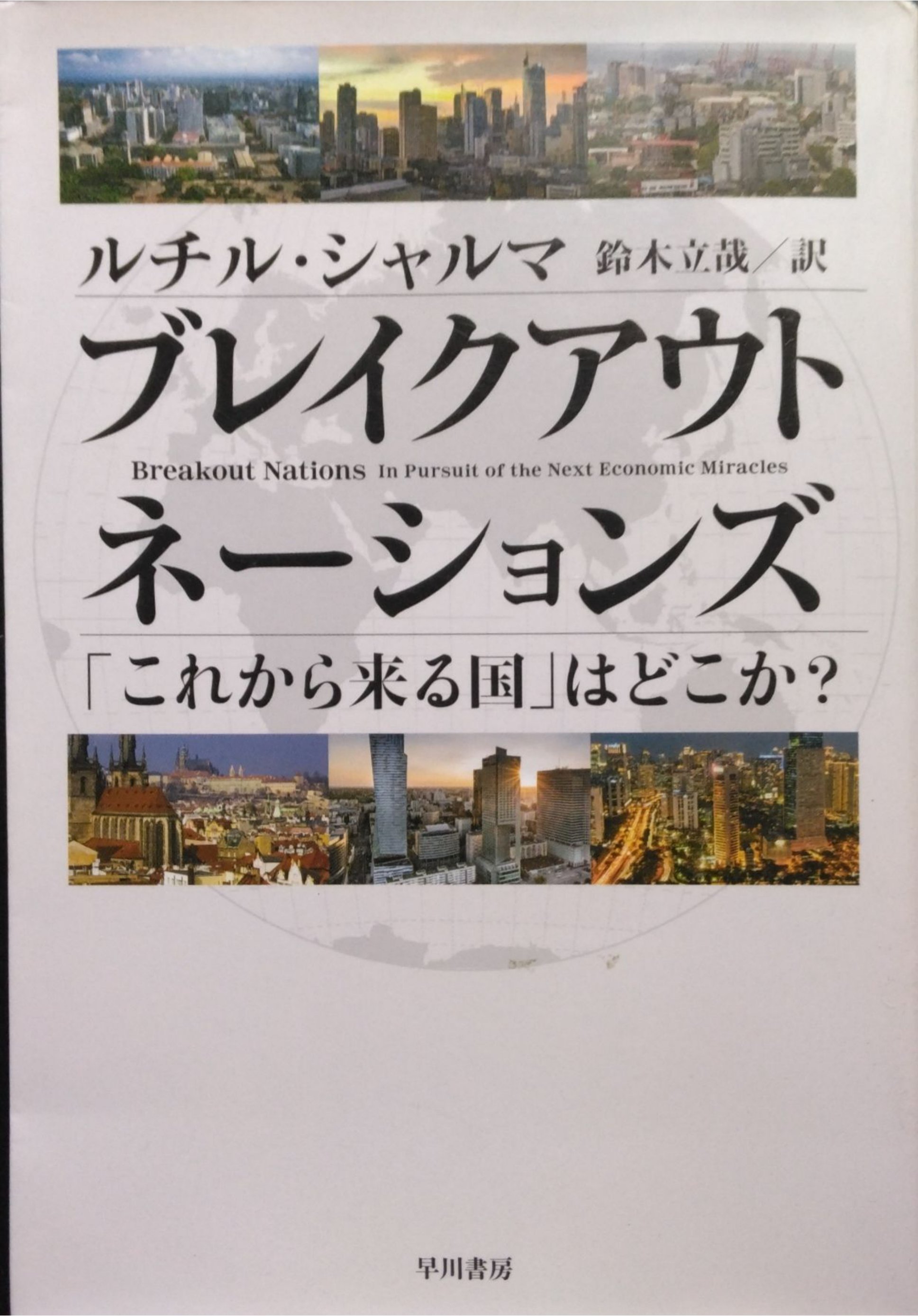 『ブレイクアウト・ネーションズ』(ルチル・サルマ) 『ブレイクアウト・ネーションズ』(ルチル・サルマ)
政治経済にはほとんど興味がないし、具体的な数字の意味あいも、細かい話も(大きな話も)、大体忘れてしまうのだけど、それでも面白かった。投資家の視点から見た、次に来る新興国、というテーマで世界を眺めた本なのだけど、それらはあくまで現地の実情(文化、風土、歴史、人間性など)に即して語られている。無味乾燥な数字を眺めているだけじゃない、手に触れられる、温度のあるものを基にした考察、ということになっている。石油に頼って経済そのものはうまくいっているが、何一つ〝ブランド〟を生みだせていない、ロシア。呆れるほどの少人数で国内企業を牛耳っている、メキシコ。人種差別を撤廃したとはいえ、ある意味ではその理念そのものが経済の足をひっぱっている、南アフリカ。戦争からようやく抜けだせた国、政治腐敗を何とか解決しつつある国、今後百年は裕福に暮らせる国――考えてみると、国ごとで経済の状況はまるで違っている。中国の話で、リニアモーターカーが出てくるのだけど(知らなかったけど、中国ではすでに実用化されていたらしい)、この未来技術の利用者はほとんどいないそうである。勢いに任せて作ってはみたけれど、という感じで、利便性ということは二の次だったらしい。とはいえ、こういう話を読むと、じゃあ日本であれだけ当然のように進められているリニアの計画って、実際はどうなんだろう、と思ってしまう。覆轍踏まず、というか、前例から学ぶべきことは多い。ちなみに、著者は日本には辛口(と言えるのか)で、国債の発行に関しては「財政改革の明白な戦略を持たぬまま、GDPの八・五パーセントという安定した平時の財政赤字を垂れ流すという、前例のない実験を続けている」と冷ややかである。正直この辺の仕組みと実情がいまいちわからないのだけど、実際のところどうなんだろう。
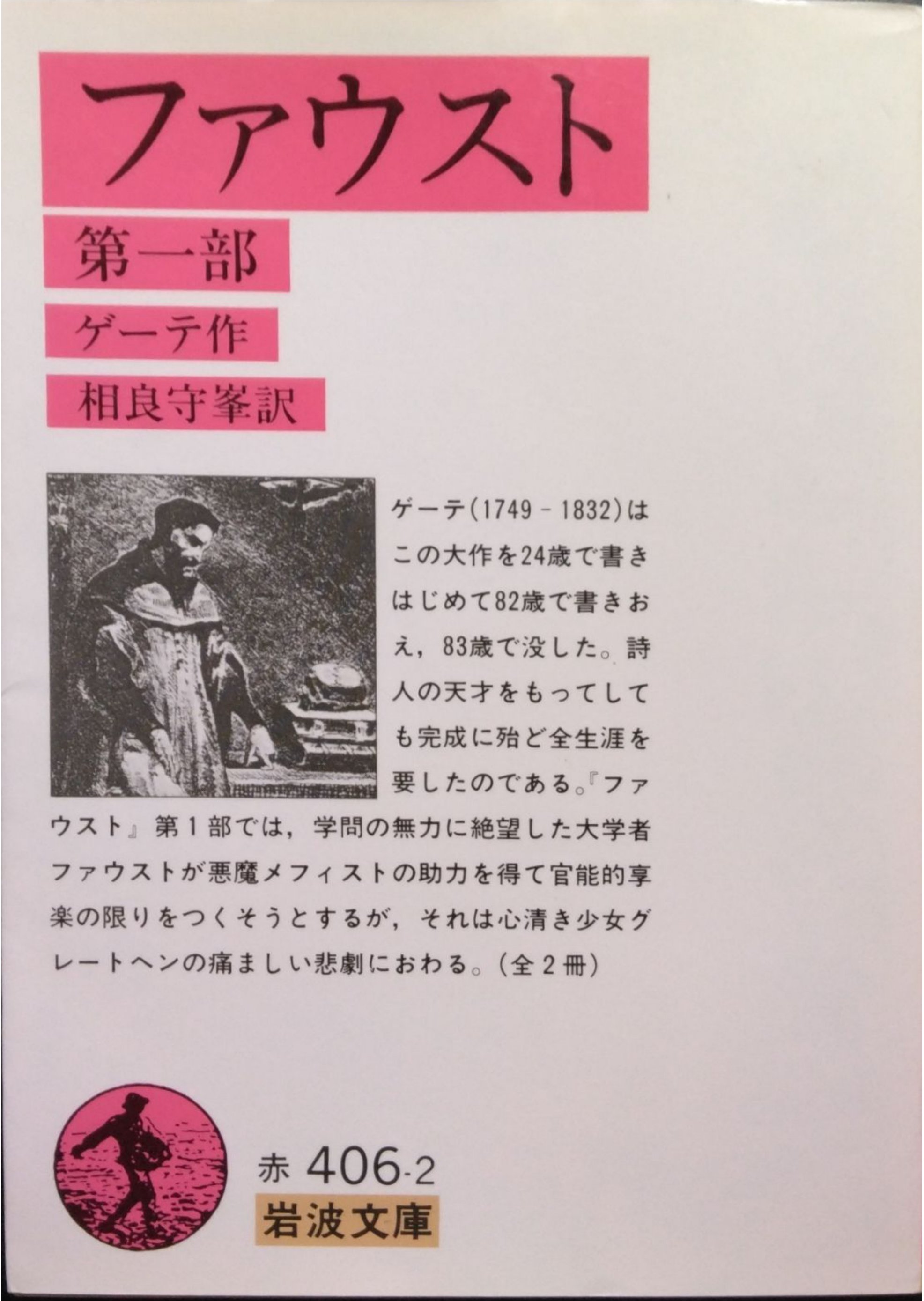 『ファウスト(第一部・第二部)』(ゲーテ) 『ファウスト(第一部・第二部)』(ゲーテ)
はじめて読んだので知らなかったのだけど、とりあえず脚本形式になっている。そして、意外と面白い。冒頭がメタ設定になっていて、座長と詩人、道化が出てきて、まずはすばらしい芝居を作ってもらいたい、という。詩人は堅物で、道化は俗物、座長はその中間、というふうにわかれている。ファウスト全体がそういう聖俗、善悪、現実と理想、みたいな両極と、その対立を描いていて、その象徴になっているらしい。神様と悪魔(メフィストフェレス)が賭けをするところは、まんまヨブ記だなぁ、とは思った。話が飛んでいるというか、「あれ?」と思うところもけっこうある。完成までにけっこうな時間がかかってるせい、もあるのかもしれない。第二部でヘレナが出てくるところは、何でまた、とは思った。ギリシャ的な美の象徴? 「時よとまれ、君は美しい」の元ネタというか、原典はこれなんだな、とはじめて知った。
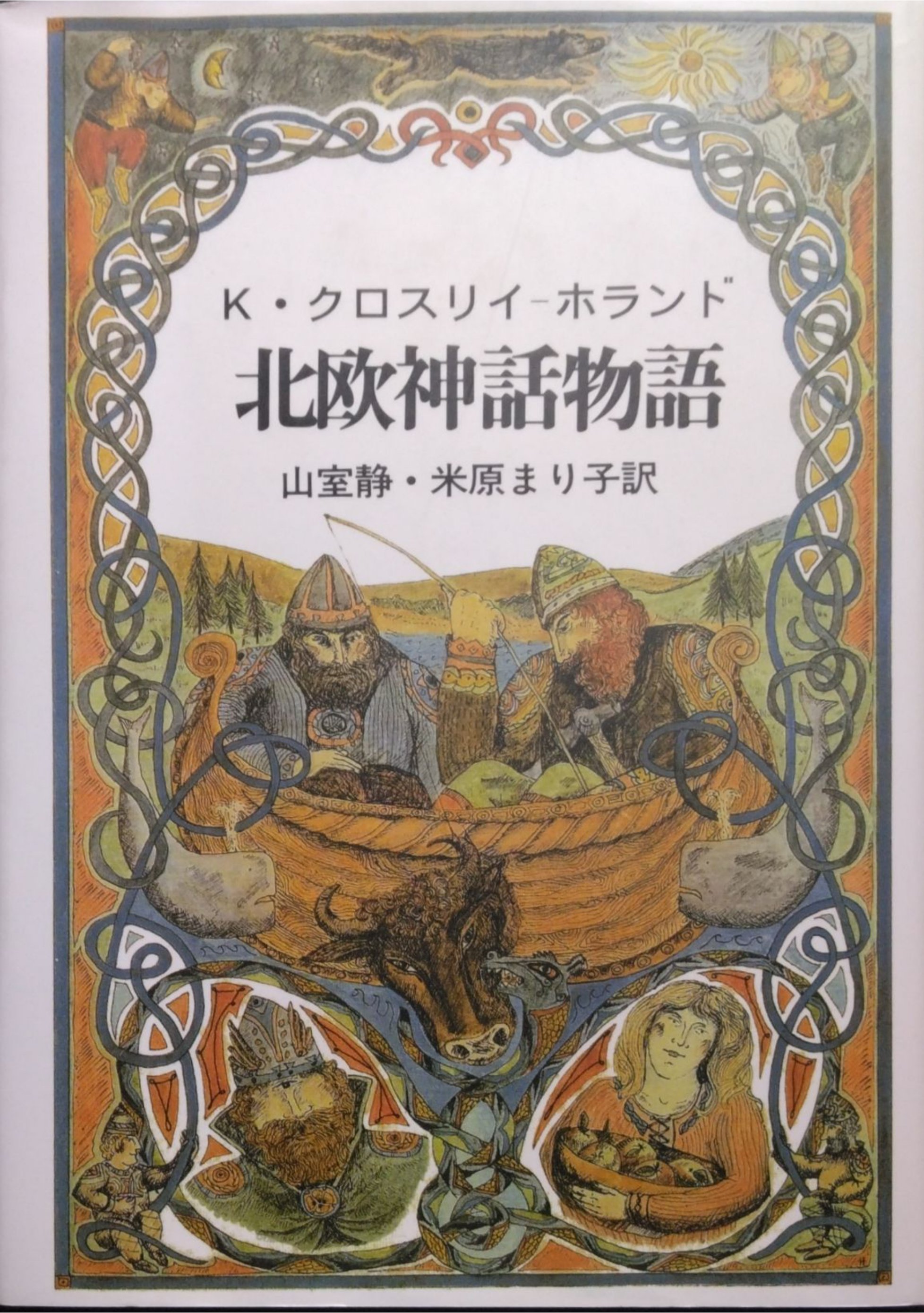 『北欧神話物語』(K・クロスリー-ホランド) 『北欧神話物語』(K・クロスリー-ホランド)
固有名詞が、がんがん出てくる。人や神の名前だの、物の名前だの、数々の二つ名だの。とりあえず、ほぼ忘れてしまった。覚えてられるわけがない。とはいえ、それが目あてだったけど。北欧神話自体は、相変わらず魅力的である。ギリシャ神話よりもっと人間くさいというか、生っぽい感じなところがある。洗練されてない、というか。語り部たちが直接に、暗い夜と焚き火のそばで語っている感じ、というか。首飾りを手に入れるために、女神が小人たちと寝る話とか、まあまあデモーニッシュだな、とは思う。バルドルが死んで、ロキが災いのもとだ、となったときに、その息子同士(ちゃんと名前がある)を殺しあわせ、その腸で岩に縛りつける話なんかも。さすがヴァイキングが作った話だよな、と思うところではあった。残酷なほどの勇気、呵責のない勝利。アウドムラって、北欧神話に出てくる牝牛の名前なんだな、とはじめて知った。Zガンダムの頃の名前をつけるセンスは、やっぱり伊達じゃないな、と。
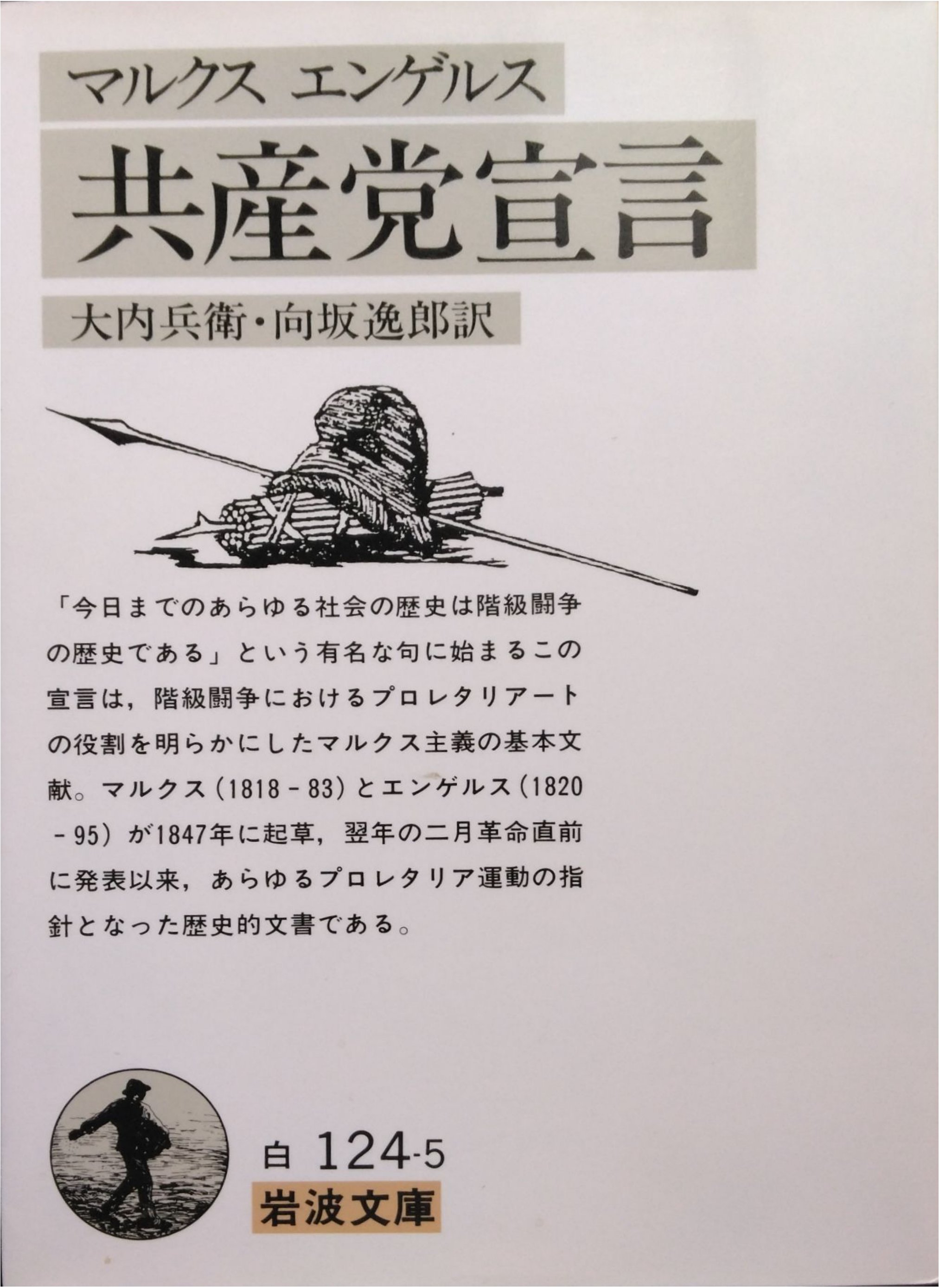 『共産党宣言』(マルクス、エンゲルス) 『共産党宣言』(マルクス、エンゲルス)
正直、どう読んでいいのかはよくわからない。当時の時代背景を知らないと、ほとんど意味をなさないところがあるのだけど、当時の時代背景がわからない。ともかく強調されるのは、ブルジョワ批判で、要するに彼らはあらたな支配階級である、と。よって、今度は労働者たちがそれと戦わなくてはならない。読んでると、何だかおそろしく機械的というか、表面的というか、ブルジョワにしろプロレタリアートにしろ、そこにあるのは「個人」じゃなくて、完全に「階級」になっている。人間性とか、境遇とか、個人的事情みたいのは、一切顧慮されない。その頑固さというか、純粋さというか、一面性は、あまり気持ちのいいものじゃないし、狂気じみたものも感じてしまう。もちろんそれは、当時の時代背景に対抗するには、それだけの覚悟なり信念なりが必要だった、ということもあるのだろうけれど。資本を個人のものではなく、社会の共有財産にしよう、というのは、要するに「個人」の否定なのかもしれない、とは思う。それは、ある意味で人間性の否定でもあるし……そんな社会がうまく機能するとは思えない。人間は結局のところ、永遠に愚かであり続けて、それを否定しても、うまくはいかないんじゃないかな、と。あと、婦人の共有とかいってるのが、意味がわからない。これ、どういう意味?
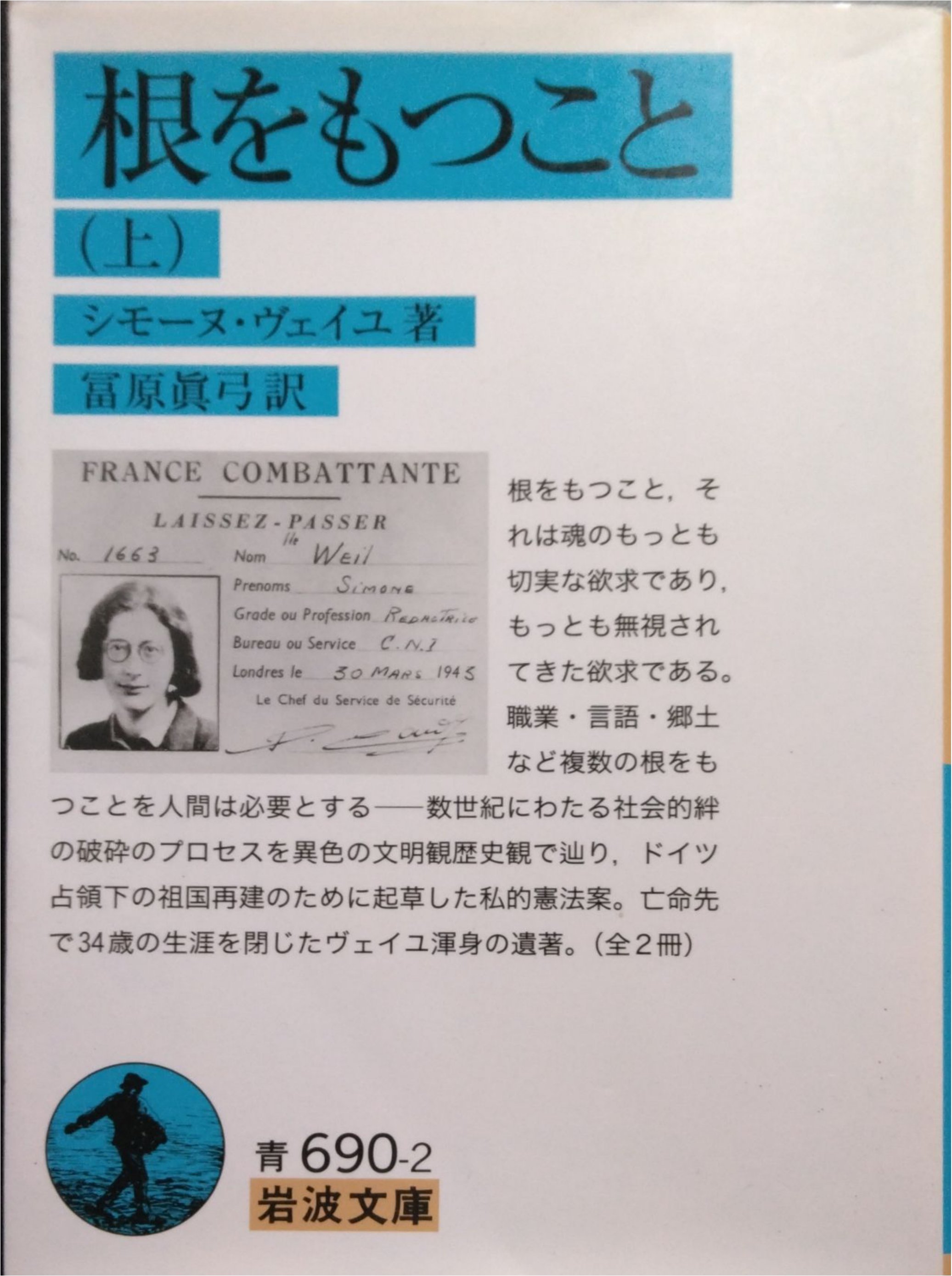 『根を持つこと(上・下)』(シモーヌ・ヴェイユ) 『根を持つこと(上・下)』(シモーヌ・ヴェイユ)
弱さの聖性、という概念にひかれて、ともかくも読んでみざるをえなかった、シモーヌ・ヴェイユ。けど、どうもよくわからなかった。よくわからなかったというか、何か、違った。あくまで政治的というか、社会的な話に終始していて、それも「フランス」と「キリスト者」ということを軸にしている。読みたかったのは、そういう話じゃなかった。根を持つこと、というのはつまるところ、望ましい帰属意識のことで、そのためには仕事と労働者の霊的(!)な結びつきや、土地と農民との結びつき、国と国民との結びつきが必要である、というようなことになる。話の趣旨が宗教的というか、あくまでキリスト教を前提にしていて、どうもその辺がしっくりこなかった。キリスト教というのは、一種の病理なんじゃなかろうか、とさえ思ってしまう。そこを出発点にする必要が、どれくらいあるんだろうか、と。それに、話の基本が工場労働者にほぼ限定されていて、何だかなとも思った。それ以外の人々は、どこに行ってしまったんだろう。とはいえ、弱さの聖性についてはまだ気になっている。
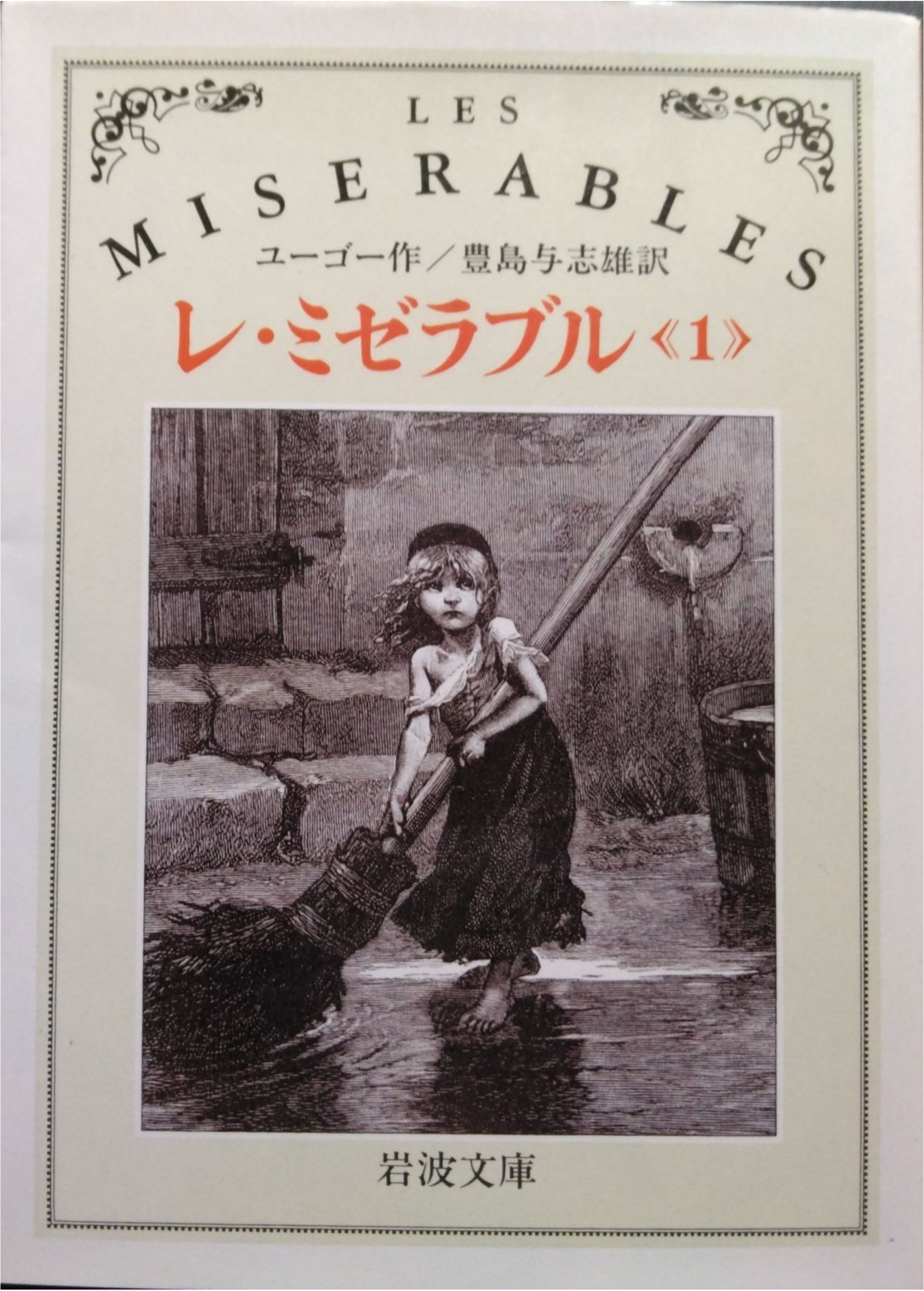 『レ・ミゼラブル(一)』(ユーゴー) 『レ・ミゼラブル(一)』(ユーゴー)
例の映画を見なければ、たぶん読もうとは思わなかった本。ともかく一読しておかなければ、とページを開いてはみたけれど、いろいろ問題はある。固有名詞が相当に多くて、当時としてはかなり意味を持っていたんだろうけど、今となってはどうにもならない、というのが多い。それはともかく、まあまあ長い。映画の冒頭あたりで「その銀器はあげたんですよ」とヴァルジャンに言う、例の司教。その司教の話が、まずがっつり書かれている。映画だと、かなりあっさりめだっただけに、わりと意外だった。ファンティーヌの話も、最初のほうからきっちりと書かれている。まあ、それはそうだろうけど。ジャヴェルに関しては、どうしてもラッセル・クロウの姿で再生されてしまって、少しおかしかった。意外と読めはするのだけど……そこまで面白いというわけではない。最後のワーテルローの長い話のところでテナルディエが出てくるのだけど、戦場で死体から身ぐるみをはいでいる。で、その死体のうちの一人がたまたま息を吹きかえして、あなたは命の恩人だ、と礼をしようとする。ところが、持っていたはずの金品は、すでにテナルディエに盗まれている、というシーンがある――ジョジョの第一部は、これを参考にしてるんだろうか?
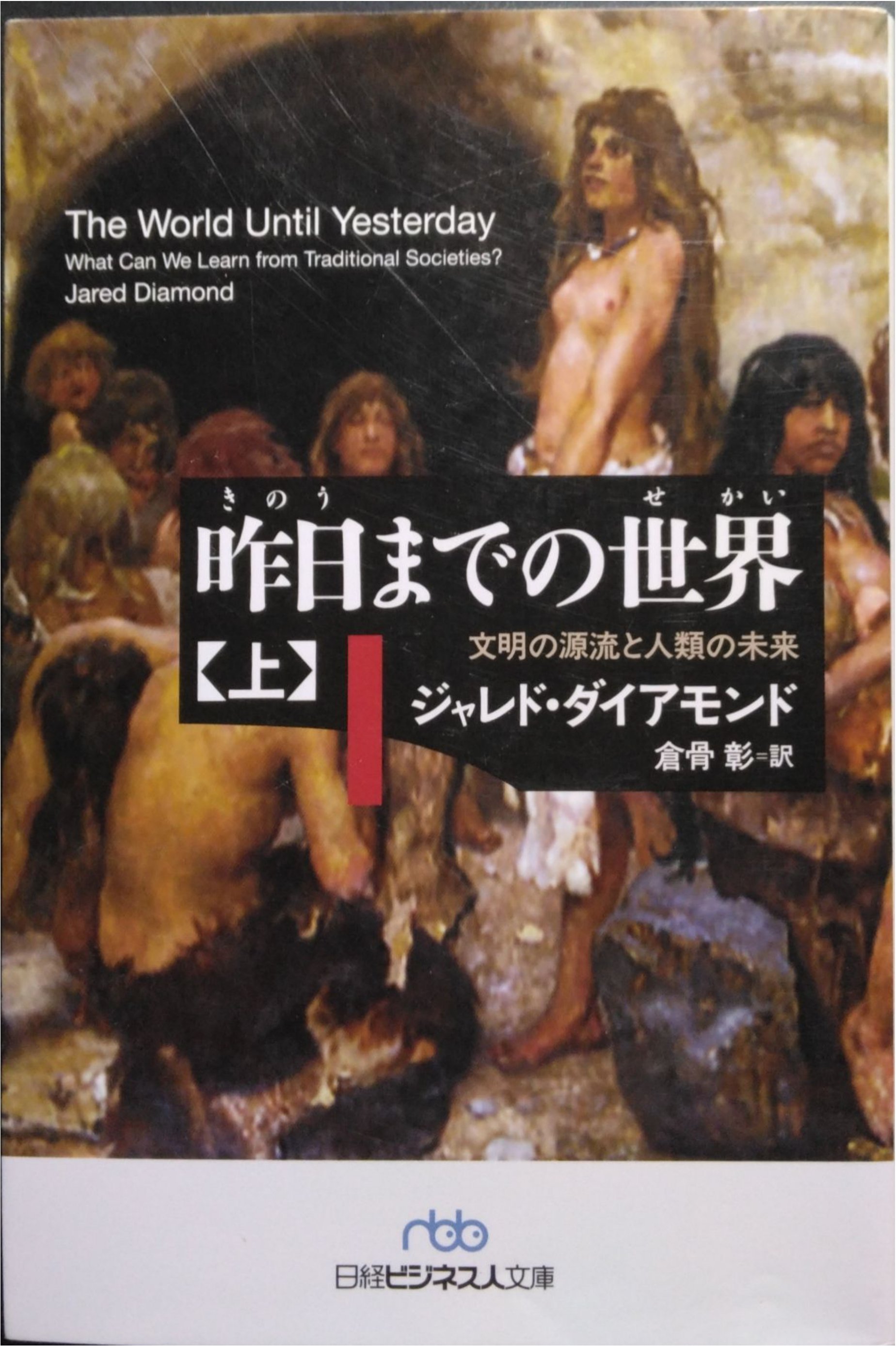 『昨日までの世界(上・下)』(ジャレド・ダイアモンド) 『昨日までの世界(上・下)』(ジャレド・ダイアモンド)
ご存知、『銃・細菌・鉄』のジャレド・ダイアモンドの著書。ただし今回はそういうマクロな話じゃなくて、あくまでミクロな、かなり身近な問題をテーマにしている。例えば、「授乳期間はいつまでがいいのか」とか。身近というか、どちらかというと個人的意見、に近い観すらある。その辺は、正直あまり素直に読めなかったというか、はたしてそれは本当に正しいのか、というふわふわした風船くらいにはっきりしない疑問が残ったりもした。とはいえ、相変わらずの学際的・横断的な知識と、理知性・平衡感覚に基づいた見識にあふれてはいる。つい最近まで(地質年代レベルで見れば)、人間は原始的な、伝統的小規模社会に属していた。そうした小規模社会は、実のところ現在でもいくつかは存続しているし、記録に残されてもいる。そうした社会には数万年の歴史があって、当然だがいくつもの進化論的実験が行われてきた。そこからは現代社会が学ぶべきことも多いのではないか、というのが基本的な話のスタンス。もちろん、伝統的社会を理想化したり、美化したりするわけではない。そこには、明らかに目をそむけたくなるような現実もあって、それは逆に現代社会をより深く理解するための照射装置になったりもする。例えば、戦争。絶対数でいえば、何十万という死者をだす現代社会のほうが、戦争の悲惨は大きいように思える。ただし、百年という期間と、人口比という相対的な数字で見るかぎりでは、実は伝統的部族間の戦争のほうが、はるかにその死者数は多くなるのである。平和、というのは、国家社会がもたらす大きなメリットであることは、明白である。というより、そうしたメリットがあるために国家社会が他の社会形態を駆逐した、というのが実情らしい。ほかにも、子育て、裁判、リスクへの対応、生活習慣病、宗教の話などなど、様々なトピックが扱われている。ただし、わりとアメリカよりというか、アメリカ社会を基準にした話、になっているところがあるので、その辺はすっきりしなかったりもする。
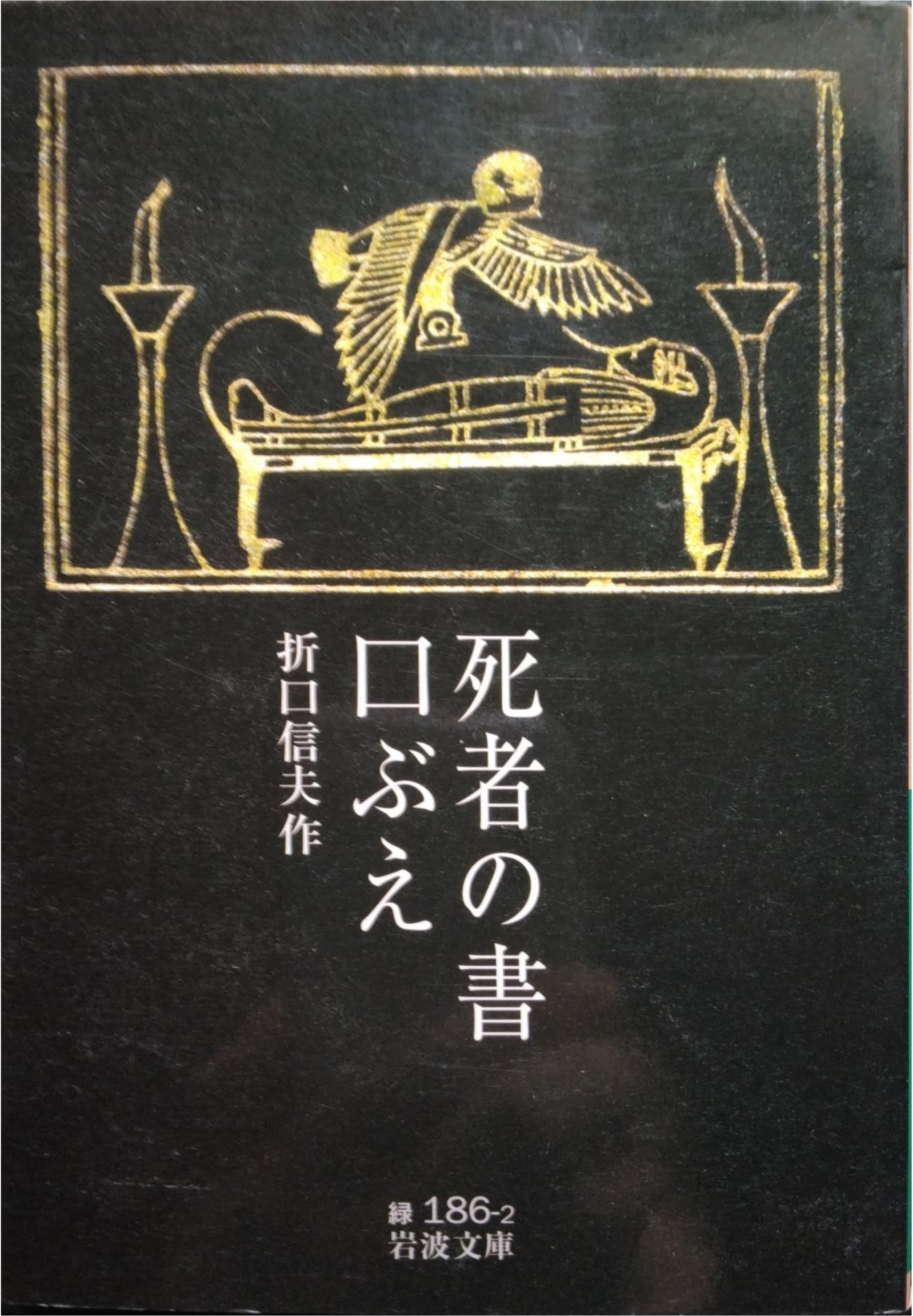 『死者の書・口ぶえ』(折口信夫) 『死者の書・口ぶえ』(折口信夫)
冒頭部分が強烈で、はじめは「これって、ある意味ゾンビ物になるんじゃないの?」と思ったけど、そんなことはなかった。実際には、死者の無念や怨念を鎮める、鎮魂小説――という感じのものらしい。正直、よくわからない。舞台背景が複雑なうえに、作中ではほとんど説明がない。細部の意味あいがとれないので、全体像も何となく曖昧になってしまう。とはいえ、特異すぎるくらいの小説であるのは間違いない。古代のロマン、というか神的雰囲気というか、異形・異世界的な空気が静かに流れている。
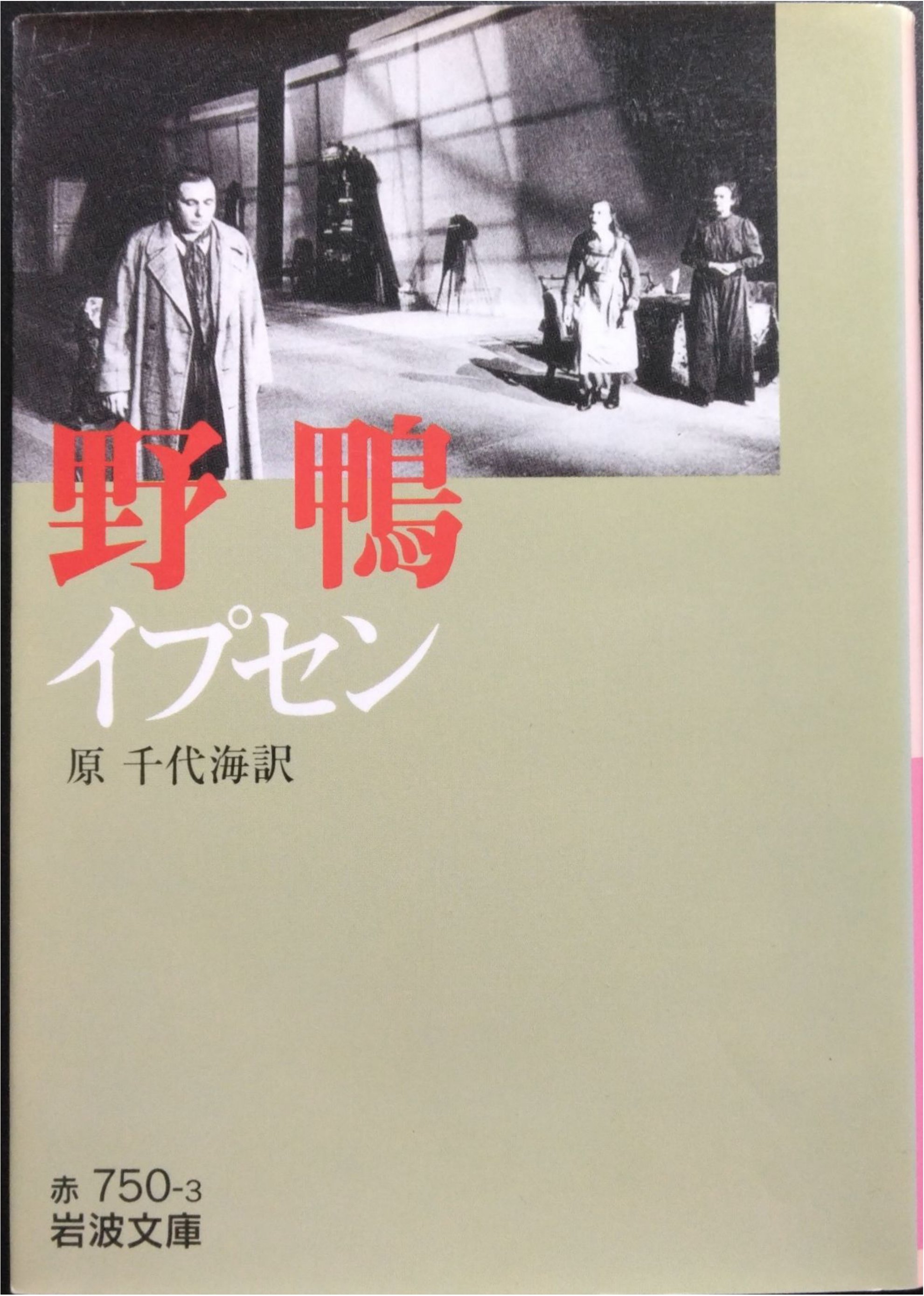 『野鴨』(イプセン) 『野鴨』(イプセン)
たぶん歴史(国語だっけ?)の教科書でおめにかかったであろう、イプセン。『人形の家』がわりと面白かったので、機会があると読んだりしている。で、これ。話をざっくり説明すると、貧しいながらも幸福な生活を送る一家に、親友がある真実を告げにくる、というもの。ある真実というのは、その一家の奥さんが、実は親友の父親と関係を持っていた、ということ。さらに話が進んでいくと、もう一つ、実はその家の子供が――最愛の娘が――父親の実の子ではない、ということがわかる。そして舞台は、ある結末を迎える。詩的な作品、ということになってるらしいけど、個人的にはむしろサスペンスとして読んでいた。少なくとも、一読した印象としては、その雰囲気のほうが強かった気がする。徐々に真実が明らかになっていく緊張感、その後の混乱と錯綜する人々の感情、それぞれの思想と思惑。何となく、ソフォクレスのオイディプスを思い出していた。決定的な破局へと着実に歩をすすめていく、その運命の足音。タイトルにある野鴨は、貧しい一家に飼われている、傷ついたノガモのこと――なんだけど、それが意味するものは、案外はっきりしない。傷ついた各々の魂を象徴するもの、ということなのかもしれない。舞台上にピストルが登場したら、それは撃たれなくてはならない、とチェーホフが(確か)言ってたけど、その通りな作品でもある。 |