|
「2022年の読書記録」 について

2022年に読んだ本は、全部で58冊。使ったのは12728円だった。
……うーん。
順調に漸減していってるところは、自分でもどうかとは思う。長い話を書いたり、直したりしていたせいもあるとはいえ。
何かが、情け容赦もなく、遠慮会釈もなく、失われつつあるような気はする。
おまけに、使える時間そのものも目減りしつつある。どういうわけかアルバイト先の人間がみんな辞めていって、その負担がこっちにまわってきているせいで。
精神的にも、物理的にも、よくなる兆しはどこにもない。温暖化やら、戦争やら、コロナやらがそうであるみたいに。
今のところ、やっぱり希望はどこにもなくて、何かがどうにかなりそうな予感もない。
道標のパンくずを鳥に食べられてしまったヘンゼルとグレーテルみたいに、暗くて深い森の中で、途方にくれているところ……なのかも。
書くことにさえ、うまく意味をつけられなくなってきている。接着力の弱くなったテープには、もう何もくっつけられはしない。言い訳を考えることすら、難しくなってしまっている。
こんなはずじゃなかった、と言うつもりはない。たぶん僕は、もう一度同じことが起きたとしても、同じことをするのだろう。
もしかしたらそれは――それでよい、ということなのかもしれない。
 『きまぐれロボット』(星 新一) 『きまぐれロボット』(星 新一)
ショートショート、というジャンルにも星新一にもあまり興味はないのだけど、かなり面白かった。ごくごく単純で簡単な、メモ帳みたいな設定に、うまいこと話をのせてくる。どうなるんだろう、どういうことなんだろう、というこちらの関心を、見事に越えてくるオチ。淡々としてるんだけど、ところどころでは質量を重くした文章。エスプリというか、芯の部分はきれいに磨いてあるんだけど、表面はあくまで柔らかく、わかりやすく整えてある。そして話はわりとペシミスティックなんだけど、悲劇的ではない。サーカスの軽業師が平気で危ういバランスを保っているような、そういう感覚。今でも全然、古びてない。頑丈で素朴な、昔の機械みたいに。
 『世界推理短編傑作集 1』 『世界推理短編傑作集 1』
江戸川乱歩編、という本。正確には、『世界短編傑作集』全三巻が『世界短編傑作集』全五巻として文庫化され、それから六十年ほどたって、いくつかの作品を追加したり、訳者を変更したりしたのが、この本、ということになる。ともかくも、江戸川乱歩が個人的な短編推理小説ベストとして選んだもの、ということは変わらない。というか、そういう諸事情はわりとどうでもいい。世界の短編推理小説を概観できる作品集、ということになっている。推理小説が特に好きということはないのだけど、面白い作品はやっぱり面白くできている。個人的に一番面白かったのは、最後の「十三号独房の問題」。思考機械と仇名されるほどの主人公が、友人との賭けで、脱獄不可能と思われる死刑囚監房をいかに脱出するか、という話。主人公のキャラ描写も秀逸なんだけど、脱出するまでの過程や、成功後の解説、その手際が面白い。もっとも、あわない話はあわなくて、ポーの「盗まれた手紙」は、灯台下暗しみたいな点がどうも納得できなかったりする。
 『超予測力』(フィリップ・E・テトロック & ダン・ガードナー) 『超予測力』(フィリップ・E・テトロック & ダン・ガードナー)
巷にあふれる専門家と呼ばれる人たちの予測は、一体どれくらい正確で、どれくらいあたっているのか? 僕たちは実のところ、そのことをあまり気にしてはいない。当面のところは感心したり、納得したり、疑問符をつけたりはするが、それが「本当にあたっているかどうか」は、ほとんど問題にしていない。よほど関心のあるトピックでないかぎり、その結果も含めて、予測そのものを忘れてしまうからだ。しかし、予測そのものは常に必要とされるわけで、ならその精度はできるだけ高いほうがよい。ところがそもそもの話、そんな「精度」をはかる基準すら問題視されてはいないのだ。何故なら、予測が的中したかどうかは、意外なほどすんなりとは決められないから。――というわけで、まずは予測の的中精度をはかるための、厳密な基準が必要になる。そのうえで著者たちがやったのは、予測的中トーナメントを開催すること。細かいことは全部省くのだけど、その結果は実に興味深いものだった。様々な仮説を立て、その検証を行いつつ、わかったのは、一群の予測者の中にはずばぬけて高い成績を示す人間がいる、ということ。そしてそういう人たちには、ある程度共通点が見られる、ということ。物事を決めてかからない、状況が変化すれば臨機応変に対応する、自分の視点にこだわりすぎない、など。例えば、予測の難しい問題に対してまず行うべきなのは、「自分はこう思う」ではなくて、「基準率」はどうなっているのか調べる、ということ。要するに、統計的にはこうなっている、というところからはじめる。そこから、細かい情報を使って予測の精度を上げていく。普通の人は、まず目の前の情報に意味づけしようとする。それだと、正確な予測は得られないことが多い。そのほか、非常に興味深いことがいろいろと満載だった。著者は例の、「投資家の予測は、チンパンジーの投げるダーツと変わらない」という研究発表をした人。ただし著者も言っているとおり、ことはそう単純じゃない。世界は実に、ややこしいところなのだ。
 『変身物語 上・下』(オウィディウス)
『変身物語 上・下』(オウィディウス)
ギリシャ・ローマ神話にはわりと興味があるので、いつかは読んでおきたかった本。ブルフィンチの、例の本の元ネタみたいな感じではあった。大体、かぶってるんじゃないかな。ギリシャ・ローマ神話の集大成、みたいな感じはある。というか、そうなのか。話が一続きになっていて、誰それの話をしていたら、そこから子供だとか、血縁者だとか、そういうふうに話が飛んでいく。何でまた、こんな形式にしたんだろう。読んでみて意外と印象深かったのは、子供を射殺された例の母親の話。ええっと、ニオベですね(名前は忘れてた)。子宝に恵まれた彼女は、レト神をあざけってないがしろにしてしまう(この女神は、アポロンとアルテミスの二人だけしか産んでいなかったから)。しかし当然、神の恐ろしい罰が下る(ギリシャ・ローマ神話では、しょっちゅう下っている)。王城にやってきたアポロンとアルテミスによって、彼女の子供たちは次々と射殺されてしまうのである。そうして、最後に残った娘を抱きかかえて、ニオベは言う。「末の子の、このひとりだけは、堪忍して! いちばん幼い、この子だけは!」。その言葉が終わらないうち、もう最後の子供も死んでしまっている……。パエトン(アポロンの息子で、太陽の馬車を操りそこねて世界中を焼いてしまう)の話なんかも、わりとかわいそうではあった。稚気にあふれただけの、無邪気な子供だったのに、とか。
 『ピクサー』(デイヴィッド・A・ブライス) 『ピクサー』(デイヴィッド・A・ブライス)
トイ・ストーリーにいたる、3Dアニメの歴史的な展開や、技術的な諸問題とその解決、ハードウェアとソフトウェアの進化、いかにして技術者たちを維持し資金を集めたか、スティーブ・ジョブズとの関係、などなど。そして、その後の快進撃。レンダリングだとかアンチエイリアスだとか、なるほどこの人たちが作ったのか、というのはあった。技術的な解説は、さっぱりではあるけど。株式の話だとか契約の話だとかも、けっこう込み入っているので、頭を素通りしているところは多い。登場人物も多めなので、誰が誰なんだか混乱していたりはする。とはいえ、草創期の、まだ3Dアニメなんて影も形もなかった頃からそれを夢見続けていた、というのはすごいことだと思う。そしてそれを実現させてしまったのは、かなり奇跡的な話なんだな、とは。初期の頃の、金持ちをだますみたいな感じで資金を手に入れてたのはどうなんだろう、とは思ったりもしたけど。ジョブズにしても、最初は映画を作る気なんてなくて、あくまでグラフィック用のコンピューターを売るためのものとして、ピクサーを買収したらしい。ピクサーそのものが、かなり波乱万丈な歴史を持ってはいる。著者がちょっとピクサーに肩入れしすぎているというか、賛美しすぎている感はあるけど、相当に細かく書かれた本ではある。
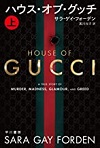 『ハウス・オブ・グッチ 上・下』(サラ・ゲイ・フォーデン) 『ハウス・オブ・グッチ 上・下』(サラ・ゲイ・フォーデン)
ブランド品に興味がなくても、およそ名前だけは誰でも知っているであろう、あの「グッチ」。その三代目社長が殺されるところから、話ははじまる。舞台は過去へと遡り、グッチ創生からその発展、一族の人間たちの複雑な関係や、会社を巡る飽くなき闘争。世界的ブランドへと躍進する一方で、会社そのものは放漫な経営や財政難に陥っていた。そこに登場するのが、三代目のマウリツィオ・グッチ。父親とのややこしい関係や、精神的な問題を抱えつつも、彼は会社のたてなおしを進める――と書くと、何だかこれからサクセスストーリーがはじまりそうだけど、最終的には会社は一族の手を離れ、投資家へと売却される。プロの経営者、プロのデザイナー、迅速に進められる再建計画。その頃マウリツィオは、会社を売った金で大金持ちとなって……そして、殺される。一種のネタバレではあるけど、逮捕された犯人は、元妻。彼女自身も相当に「やばい」人ではあるけど、その動機は恐ろしいほどに子供っぽい。冗談みたいな殺害計画、放埓そのものな生活。それでも、殺害から二年が経過してはいた。彼女の裁判が行われる一方で、グッチそのものは奇跡的な成長を続ける。ライバル企業の買収をかわし、様々なブランドを傘下に抱え、巨大企業へと。しかしまあ、巨大企業の世界って、戦国時代と変わらないんだな、という気はした。攻撃、防御、だまし討ち、横槍。まったく、変な世界ではある。正直なところ、ブランド品にはまったく興味がないけど、実に神話的な世界ではあった。グッチといえば中世の宮廷で馬の鞍を作っていた、という伝説があるのだけど――嘘らしい。ただし、馬具をもとにデザインしていたのは、真実。
 『湿地』(アーナルデュル・インドリダソン) 『湿地』(アーナルデュル・インドリダソン)
アイスランドを舞台にした、陰鬱で、陰惨で、奇妙に静かなミステリ。主人公は、捜査官のエーレンデュル(ちょっと独特な名前の人が多い)。湿地にあるアパートで殺された、一人の老人。当初は典型的な「アイスランドの殺人」と思われていたその事件は、どんどん底なしに深くなっていき、やがて一つの終端的な悲劇へと至る。それは、人類そのものに深くかかわった「業」みたいなものなのかもしれない。文体は、簡潔だけど芯が丈夫で、金属的な感じといっていいかもしれない。頑丈で無愛想だけど、表面に傷のない、そういう金属。殺人事件が最終的に行きつくところは、わりと伊坂幸太郎の「重力ピエロ」を連想してしまうところはあった。少なくとも、ある種の要素については。
 『鹿鳴館』(三島 由紀夫) 『鹿鳴館』(三島 由紀夫)
表題作を含めて、四編の戯曲を収めた作品。三島由紀夫に特に興味があるわけではないのだけど、面白かった。「鹿鳴館」に出てくる影山は、かなり興味深かった。ほとんど機械神みたいな存在感を放っている。最後に朝子が「おや、ピストルの音が。」と言っているのは、実際には何が起きたのか気づいてるってことなのかな……。「只より高いものはない」は、何となく昼ドラ風ではあった。奥さんが手鏡で光を当ててるところは、相当不気味な光景ではある。最後のやりとりも、かなりすさまじいところがある。えぐい。「夜の向日葵」は、君子のキャラがすごい。これだけ限界に近い天真爛漫さって、なかなか書けるものじゃない気はする。三島文学とかよくわからんけど、ともかく面白かった。ところで、何でこの本を読んだかというと、実は志村貴子の「青い花」に出てくるから。文化祭だかで演じられるお芝居で、「何でまた鹿鳴館なんだ?」と長いこと思っていた。何で鹿鳴館なのかは、今でもよくわかっていない。
 『僕の名はアラム』(サローヤン) 『僕の名はアラム』(サローヤン)
サローヤンの作品は何冊か読んだけど、よくわかっていない(というか、よく覚えていない)。けど、この作品は面白かった。古い、古い、僕らにはもうずっと遠くなってしまった、けど本当はそれほど遠くはない世界の話。少年の、本当に少年にとっての世界。未来も過去も、どっちも必要ないくらい、自分が自分自身でしかなかった世界。そういう一つの時代、一つの在り方が、タイムカプセルからそのまま現れたみたいに書かれている。少年らしい賢さと愚かさ、単純さと複雑さ、混乱と秩序。剽軽であり、素朴であり、意外なほどシンプルで根深いペーソスが含まれていたりする。はちゃめちゃだけど、小説的なクオリティの高い作品。そして、奇妙に「とぼけた」感じのする文体。
 『オープンサイエンス革命』(マイケル・ニールセン) 『オープンサイエンス革命』(マイケル・ニールセン)
理想的にいえば、すべてのデータは公表され、誰でもアクセス可能で、思いついたアイデアは共有され、自由な討論が行われ、そして最善の結果が導きだされるべきである――が、実際にはそうはいかない。苦労して得られたデータは自分たちだけで使いたいものだし、せっかくのアイデアを他人に利用されてはかなわない。そんなことには何のメリットもないし、自分たちが損をするだけだ。……だけど、それがうまくいく場合もある。これは、そのことについて考察された著作。いわゆる「集合知」についての話で、その成功例や、具体的な方法、その経過、それから失敗例なんかについて具体的に言及している。牛の体重を推測するのに、群集の意見の平均値をとると、それは驚くほど正確な値を示していた、という例の話のとおり、「三人寄れば文殊の知恵」的な話は実際に存在する。ただし、それほど単純でも簡単な話でもなくて、きちんとしたシステム、管理者、苦労と努力が必要になる。けれどそこから得られるものは、人類の可能性を大きく広げてくれるかもしれない――。現代の科学は基本的に論文が中心で、それは過去の秘密主義からの脱却のためのものだった。とはいえ現在、それは助成金の獲得手段という、別の弊害をもたらしている。だから誰もが、秘密主義になっている。制度そのもの、人々の意識そのものを変える必要があるのだけど……そこは難しいだろうな、という気はする。個人的には、「特許」は本当に必要なのか、というのが気になっているんだけど、そういう話はなかった。これはむしろ、人間の「動機」の問題でもある気はする。
 『少年たちはなぜ人を殺すのか』(キャロル・アン・デイヴィス) 『少年たちはなぜ人を殺すのか』(キャロル・アン・デイヴィス)
実に暗澹たる、救いのない気分になれる本。世界がどれだけまともじゃないのか、というのがよくわかってしまう。虐待され、尊厳を奪われ、異常な扱いを受けてきた子供たち。彼/彼女たちは、やがて世界に対して〝それ〟を返すことになる。もちろん、それは特殊なケースで、すべてがそうなる、というわけじゃない。けど結局のところ、誰かを殺す子供より、親に殺される子供のほうが、ずっと数が多い、というのが事実ではある。そしてその親たちにしろ、同じくらい暗澹として、救いのない人生を送ってきている。いわゆる虐待の連鎖というやつで――その鎖は頑丈で、断ち切るのが難しい。家族というものに対する習慣的思考、虐待を防ぐための制度や関係者の不備、被害者である子供がうまく証言できないこと。それでも僕たちは、少年たちの行為だけを取りあげ、その背景について知ろうとはしない。たぶん僕たちは、「殺してしまった彼ら」より「殺されてしまった彼ら」に感情移入しやすくできているからだろう。報道機関にしても、大抵はそういう方向で終始することになる。個人的には、本物のサイコパスは存在すると思うけど、それでも虐待そのものが罪にならないわけじゃない。
 『デジタル・ミニマリスト スマホに依存しない生き方』(カル・ニューポート) 『デジタル・ミニマリスト スマホに依存しない生き方』(カル・ニューポート)
実のところ、僕がスマホを持ったのは、去年(2022年)の一月末日頃のことになる。スマホなんてなくても、死ぬわけじゃない。替えたのは、古い携帯の電波が使えなくなるので、無料で機種交換をしてくれる、ということだったから。スマホを使いはじめた当初は、死ぬほど使いにくいし、設定のしかたがさっぱりわからなかったりしたけど、慣れるとそういうこともなくなった。というか、写真で検索をかけられたりするのは、かなり感動的だった――というのは、余談。ただし、この本に書かれているとおり、スマホは「スロットマシーン」である、というのはわりと納得できている。意味もなく電源を入れたり、意味もなくアプリを起動したりする。そういうもんだよ、と思うかもしれないけど、実は違う。何故なら、企業はそれを意図しているから。彼らは、人々が嫌でもスマホをいじらずれいられないように仕向けているのだ。それを理論化したのが、「間歇強化」と「承認欲求」である。「間歇強化」とは、要するに時々「当たり」が出る、ということ。有名なハトの実験で、ハトはランダムに餌が出てくるボタンのほうをたくさんつついた。ネット上のコンテンツはほとんどが自分には無関係だったり、必要ではなかったりするけれど、時々は「当たり」が出る。そのせいで、僕たちはつい無駄な時間を費やすことになってしまうのである。「承認欲求」は、読んで字のごとし。社会的な存在である人間は、他者の評価を気にするようにできている。それ自体はまったく順応的な反応ではあるけど、不必要だろうと意味がなかろうと、僕たちはそれを無視することができないようになってしまっている。……というわけで、僕たちは正しい「戦略」を持ってこれに対処しなくてはならない。何故なら、企業は消費者が「時間」を使ってくれるよう、全力をもって企図しているから。彼らはそれによって、「お金」を得ているのだ。その実践方法や、具体的なアドバイス、いくつかの哲学的思考を提示しているのが、この本。政府は小学生にタブレット端末を配る前に、この本を読ませたほうがいいのかもしれない。
 『複雑系』(M・M・ワールドロップ) 『複雑系』(M・M・ワールドロップ)
正直、カオス理論のことを「複雑系」だと思っていたのだけど、そういうことじゃないらしい。複雑系が扱う分野の一つが、カオス理論……ということなんだと思う。何にせよ、「複雑系」の根幹に在るのは、「何故、世界は複雑なのか?」という問いになる。何故、細胞は複雑化して生物になったのか、何故、取り引きは複雑化して市場になったのか、何故、人間の関係性は複雑化して社会になったのか。つまるところ何故、世界はこのようなのか。そこには多種多様な物質があり、生物がいて、あまたの関係性によって結ばれている。エントロピー増大の法則に従えば、世界には無が訪れるはずなのに、実際にはそうなってはいない。絶えず、何かが生みだされている。どうやらそこには、共通した原理が存在するらしい、というのが一つの結論になっている。世界は複雑化するようにできている、と。そのキーワードは、創発や自己組織化やカオスの縁。ちょっと驚くほど、それらの原理は共通している。そこにはたぶん、科学的に厳密な定義づけができる「何か」がある。この本に描かれているのは、その「何か」を求めて様々なアプローチをする、多方面の人々である。経歴も、専門分野も、生まれも育ちも違うそれらの人々は、ただ「複雑系」の解明という一点において共通している――。研究者自身によるコメント、現場の詳細な雰囲気、科学的な解説、研究所としての経営問題、そういったことが、丁寧に詳細に描かれていく。正直、誰が誰なんだかよくわからないところはあるけど、ともかく面白い本だった。 |